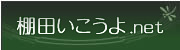こんにちは!
幹部紹介に引き続き、本ブログも今村がお届けします。
まだまだ新米部員(棚けんだけ…^^;)のつもりでいましたが、私も春から3年生。
時の流れは早いですね。
と、ここから本題!
今日から4日間に渡って一年生紹介をしていきます!
1年生紹介を楽しみにしてくださっていた方々、投稿が遅くなってしまい、本当に申し訳ありません…!
今年度の1年生は、明るく元気で、とっても頼りになる魅力的なメンバーばかり!
それでは早速行ってみましょう!
質問は以下の通りです↓↓↓
①名前
②学部学科
③出身
④棚けんに入ったきっかけ
⑤ごはんに1番合うと思うおかず
================================
①石原みずき
②人文社会科学部経済学科
③沼津市
④友達に誘われ、楽しそうだったから
⑤鮭
▶︎沼津市と言ったらやはり沼津港!そして、沼津港といえば、そう!海鮮丼!
海の幸とごはんの相性は抜群ですよね。沼津で食べるお魚、美味しいんだろうなあ…
ぜひ今度おいしいお店紹介してください!
①伊藤ひびき
②農学部応用生命科学科
③愛媛県
④なんか楽しそうだったから
⑤イカの塩辛
▶︎イカの塩辛、渋いですね。正直、あれは罪な食べ物だと思っています。(良い意味で)
棚けんのお昼は基本スイハニングで、たくさんごはんを食べることができます。
イカの塩辛を持って行ったら全部平らげることができちゃいそうです^^
①乾
②農学部生物資源科学科
③愛知県
④もともと棚田に興味があり、実際にそこでお米作りの体験をしてみたいと思ったため
⑤大根のきんぴら
▶︎もともと棚田をご存知だったとは…とっても嬉しい!
棚けんではお米づくり以外にも、あぜ道アートや蕎麦打ちなどの普段はできない体験をすることができます。
棚けんで一緒にたくさんの思い出作りましょう!
①大岩胡春
②農学部生物資源科学科
③栃木県
④自然が多くて気持ちよさそうだと思ったから
⑤しょうが焼き
▶︎四季折々の風景や澄んだ空気。せんがまちに行けば心が癒されます。
また、普段は見ることができない貴重な生き物に出会えるところも魅力の一つです。
今年はカモシカ見られるかな?また見つけたら教えてください〜!
================================
今回はここまで!
明日もお楽しみに〜♪
今村がお届けしました。