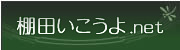※必ずメ ールにてお申し込み下さい。下記「お申し込み方法」参照。
草刈り・草取りの午後は、和紅茶づくり体験に!
世界農業遺産「茶草場農法」で育てた茶葉を使って、紅茶をつくってみま
しょう。小さなお子さんでもできる体験プログラムです。
★午前中の草刈り・草取りへの参加も大歓迎です!
詳しくはこちら↓
https://www.tanada1504.net/sengamachi/archives/9971
■日時
2017年7月8日(土)13:00~15:30
(12:45~公会堂前で受付開始)
■会場
倉沢の棚田せんがまち・上倉沢公会堂
(菊川市倉沢1121-1)
アクセスはこちら
https://www.tanada1504.net/access.html
※駐車場もございます。上倉沢公会堂向かいの広場をご利用ください。
■内容
和紅茶づくり体験
講師:堀 延弘さん(NPO法人せんがまち棚田倶楽部事務局長)
■対象
せんがまち棚田オーナー
棚田保全・自然体験・農業体験に興味のある方
■定員
20名
■参加費
せんがまち棚田オーナーメンバー 無料
その他の方 お一人様500円(小学生以下無料)
■持ち物
特にありません。
■お申し込み方法
下記、メールアドレスに件名「7/8和紅茶づくり」とし、①代表者お名前 、②参加人数、③棚田オーナー○・× を明記の上お送りください。
※棚田オーナーでお申し込みいただく方は、一緒にご参加されるメンバーの方も含めてお申し込みください。分担してお申し込みされた場合、オーナー以外として受付させていただきますので、ご注意ください。
※今回ご提供いただく個人情報は、適正に管理し、プログラム実施の目的以外で使用いたしません。
―メール―――――――――――――――――――――
NPO法人せんがまち棚田倶楽部 事務局
担当/天野
amano★tanada1504.net
★を@に変えて下さい。
―――――――――――――――――――――――――
■主催
NPO法人せんがまち棚田倶楽部
https://www.tanada1504.net/
■協賛
菊川市茶業協会
http://kikugawacha.com/
みなさんのご参加、お待ちしております!お茶農家の仕事をちょこっと体験してみましょう!
投稿者 あまの
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
参加者募集中です!
7/8(土)草取り・草刈り保全作業
年間予定はこちら↓
https://www.tanada1504.net/owner.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■